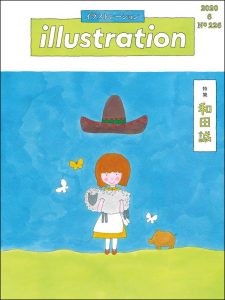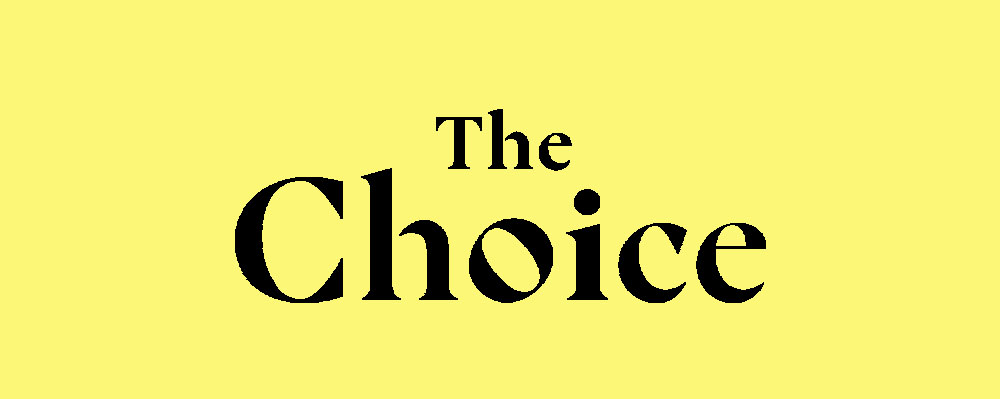近年、村上春樹さんの新刊『猫を棄てる 父親について語るとき』(文藝春秋)の挿画を手がけますます話題になった、台湾出身のイラストレーター高妍(ガオ・イェン)さん。
幼い頃から絵を描き続けてきたという高さんの作品は、SNSやZINE、手がけた仕事をとおして海を越え、いまやさまざまな場所に届いています。台湾で生まれ育った彼女は日々何を考え、感じ、どのように制作しているのでしょうか?(このインタビューは『イラストレーション』No.226に掲載された連載「Artist in The World Number 10」を抜粋し、ご紹介しています。)
取材協力: 大松芳男(株式会社文藝春秋) 大林えり子(ポポタム)
制作は“実行”ではなく“思考”
――絵を描き始めた頃から現在までのことを教えて下さい。
物心付いた頃からずっと、絵を描くのが大好きです。祖母と母が芸術に関する学校に通っていたので、家庭の影響とも言えるかもしれません。絵の道を長く続けていきたいと決意した時、彼女たちは反対するどころか支えてくれました。そういうわけで、美術科のある高校で毎日油絵や水彩画やデッサンの世界に浸ることが出来たんです。そして、その後も順調に台湾芸術大学の視覚伝達デザイン学系に進学しました。
書籍やバンドのCDジャケットのデザインやイラストレーションを描く仕事がしたかったので、大学入学当初はイラストレーターやデザイナーになりたいと思っていました。ただ大学では時代遅れな教育システムや指導方法を採用していたので、学びのある環境ではなく、自分の表現も認められませんでした。それで、はからずしも大きな失望を感じてしまったんです。大学への憧れを一瞬にして失ったことで、出来る限り授業をサボるようになり、絵を描く意欲もなくしてしまいました。その代わりにインディーミュージックに夢中になり、小説や漫画や音楽に囲まれて過ごす日々がしばらく続いたんです。
再び創作意欲を燃やすきっかけとなったのは、初めて台北の漫画喫茶「Mangasick」(*1)に行った時のことでした。そこで「こんなにも面白い創作の形があるんだ」と、それまでに感じたことがなかった衝撃と気付きを得て、自費出版物、いわゆるZINEを作り始めます。そうするうちに自然と作品が増えていき、SNSを通じて依頼されたイラストレーションや漫画の仕事をどんどん引き受けるようになりました。そんな風な成りゆきで、イラストレーター・漫画家になったんです。
*1 Mangasick…2013年オルタナティブ・サブカルに特化した漫画喫茶としてオープンし、現在はZINEの販売やギャラリースペースでの展示、リトルプレスの出版なども手がける。Twitter@mangasickmanga
――現在は主にどういった活動をされているのですか?
職業としてはイラストレーター・漫画家ですが、今年大学を卒業したばかりです。昨年沖縄に留学したことで、1年卒業が延びてしまったので。
大学の時はイラストレーションや漫画を描いてZINEを作るなど、インディーで出版活動をしていましたが、最近は出版社との仕事も増えています。2020年2月には台湾パビリオン代表としてアングレーム国際漫画祭にも出展しました。また、2021年に初めての単行本を台湾で出版する予定で、日本での漫画連載も相談中です。
――絵を描く時、どのようにイマジネーションを膨らませるのでしょう。
イラストレーションにせよ、漫画にせよ、たいてい時間をかけるのは“実行”ではなく“思考”です。絵を描くより、音楽を聴く、映画を観る、小説や漫画を読むことに時間を使います。たくさんの素晴らしい作品から刺激を受け、脳内を豊かにし、それを凝縮して創作に転化するんです。素敵な木の形や水の動きなどの風景を観察しながら、構図を考えたりもします。座って仕事を始める頃には頭の中に完成形が見えているので、あとはただ描き出すだけです。
とはいえ、そんな“思考”は創作のためにわざわざ行うわけではなく、生活の一部として存在しています。私は2014年からずっと日記を書き続けているんですよ。日記とはいえ、エッセイみたいな書き方で生活のなかで心に触れた瞬間を記録していて、私にとってその「日記」はすべての創作の基本と源泉です。だからこそ、いままでに描いた漫画作品のだいたいはノンフィクションだったんです。魅力溢れる優秀な創作者になるための前提条件は、絵のうまさよりも物や感情が発する“リズム”を感知する感覚の鋭さだと思っています。
――使用している画材や道具はどんなものですか?
Photoshopで水彩っぽいブラシを使って描くのでアナログっぽく見えますが、たいていはデジタル作画です。使っているのは、13インチのMacBook Proとワコムの一番小さくて軽いペンタブ。小学校6年生の頃から簡単なソフトを使って絵を描いていましたし、もともとデザイン専攻で本格的なデジタル作画に触れたのもとても早かったので、作画の基礎がデジタルなんです。その反面、アナログでの制作に憧れる気持ちもあります。沖縄県立芸術大学に留学した時には美術学部絵画科油画専攻を選んで、とても楽しい1年を過ごしました。シルクスクリーンや木版の授業を取って、版画作品を作ったりもしたんですよ。それを観た東京のタコシェ(*2)の店長さんが興味を持って、2020年に版画作品の展示をやろうと誘って下さいました。
*2 タコシェ…東京・中野ブロードウェイにある、ZINEや一般流通にのらない書籍、インディー系のCDや映像、絵画、雑貨を取り扱うショップ。展覧会やイベントも行っている。http://tacoche.com
「風を集めて」と“緑”
――好きな小説や映画、音楽、またその影響について教えて下さい。
音楽、映画、小説や漫画の世界に浸るのがとても好きです。私の作品をご覧になったことがある方なら、きっと私がどのくらい音楽が好きなのか感じられるでしょう。自費出版した『緑の歌』と『間隙・すきま』も、細野晴臣さんと1970年代の彼らのバンド・はっぴいえんどの音楽から着想した作品です。簡単に言うと、これは“偶然”と“愛”の物語です。主人公は何気なくはっぴいえんどの「風を集めて」を聴き、偶然レコード屋で流れていた細野さんの音楽と出会い、まるで彼の音楽に恋をしたような気分になります。そして、台湾でライブを開催したことがなかった細野さんが70歳にして初めて台湾ツアーを行うことになり……というストーリー。2018年2月に台湾華語で出版した時には日本で売っていなかったはずなのに、なんとはっぴいえんどのドラム・作詞家の松本隆さんの手に渡って、SNSでちょっとした話題になったのです。松本さんのおかげで、2回目の台北ツアーの時にMangasickで細野さんにも初めてお目にかかることが出来ました。さらに細野さんのドキュメンタリー「NO SMOKING」の撮影にも参加し、ライブの時も楽屋に何度もお邪魔させて頂いて、感謝しかありませんでした。『緑の歌』は私の人生における最初のピークなんです。2018年9月にはMangasickから出版された邦訳版が日本各地の書店で販売されたので、私に注目して下さる日本の方々も増えました。


――『猫を棄てる 父親について語るとき』のお仕事はどのようなものでしたか?
人生2回目のピークはこのお仕事に違いないです。2019年11月末に編集の方からメールで依頼があり、『文藝春秋』2019年6月号に掲載された村上春樹さんのエッセイを書籍化するにあたって、表紙と挿絵を担当させて頂くこととなりました。メールを受け取った時はあまりの驚きに、叫びながら手の震えを抑えていないとメールが読めないくらい興奮し、本当にうれしかったです。「どうして私なの? 嘘だろう!」と。村上さんの書籍にイラストレーションを描くなんて、考えたこともありませんでした。読者として見ているだけでも十分幸せだったのです。
というのも、私は村上さんの作品にいろいろな影響を受けていて、自分で制作した本でもよく彼の文章や言葉を引用したり、言及したりしていました。実は『緑の歌』の“緑”は、村上さんの小説『ノルウェイの森』(講談社)のキャラクター“小林緑”から引用したものです。また、『ノルウェイの森』は私が初めて日本語で読んだ小説であり、いままでで一番何度も読んだ小説でもあります。『間隙・すきま』の後書きでも、『ダンス・ダンス・ダンス』(講談社)のセリフを引用しました。また、今号特集されている和田誠さんと安西水丸さんは、村上さんの作品とのバランスや雰囲気がキラキラと輝くような組み合わせで、私にとって憧れのイラストレーターでした。だからこそ、突然とんでもなく大きな仕事を頂いて芽生えた責任感がだんだんとプレッシャーに変化していきました。
そうして仕事を進めている途中、アングレーム国際漫画祭に出展するためにパリに行ったんです。さまざまな博物館や美術館はとても刺激的で、教科書でしか見たことがなかった印象派やアール・ヌーヴォーなどの作品を観ることが出来、とても感動しました。一方、自分の描いた絵はまだ足りないなとずっと悩んでいました。いろいろと考えた結果、帰国してすぐ編集者さんとデザイナーさんにもう1度描き直したいと唐突なお願いをしたところ、お2人は十分な時間を下さいました。その後、3~4回のやりとりを重ねて、やっとの思いで表紙と挿絵を完成させることが出来たんです。流暢ではない日本語でのやりとりに寛容に接し、私を信頼して自由に創作させて下さったこと、心から感謝しています。
それ以外にもいままでにあった素晴らしい出来事やお仕事の依頼などは、頭の中に絵のことしかなく、ただ必死に描いてきた私にとっては夢にも思わなかったことなのです。このすべての奇跡は、「創作の力が私たちをもっと遠くて、想像出来ないところまで連れていく」ことの証明です。道に迷っても辿り着くまで諦めず、ずっと歩いてきてよかったと、心からそう感じています。最初は小さな声かもしれないけど、私たちの精神は作品をとおして海を越えて運ばれ、最後は巨大な共鳴と共に自分に還ってきます。実は私にとって絵を描くことは、とても重々しくて息の詰まるものなのです。面白い漫画や作品を描くのはとても難しいことで、構図や絵のタッチ、どうやって紙とペンで音を伝えられるのかなど、頭の中はそういった考えでいつもいっぱい……。私はただ負けず嫌いなだけで、才能のある人間ではないのです。
自由とは空気のようなもの
――アーティストが政治的な発言をすることを、台湾では、また高さん自身はどのように考えていますか?
チリ出身の映画監督アレハンドロ・ホドロフスキーのこんな名言があります。「籠の中で生まれた鳥は飛ぶことを病気だと思ってしまう(Birds born in a cage think flying is an illness)」。
自由は空気のようなものであり、それが消えて窒息して初めて自由という存在に気付くのです。私はたくさんの自然や熱心な住民に囲まれて、小さいけれど豊かな台湾で23年間生きてきました。台湾は自由と民主の国であり、選挙に参加する権利と言論の自由を持っています。また、アジアで初めて同性婚を合法化した国でもあります。
反して、私たちの隣には不自由、不民主の国がありました。毎日私たちを邪魔したり、国際的に圧迫したりして、アジア全体の平和を損なっています。日本人にとって台湾の立場は分かりづらいかもしれないけど、私たちはそういう寄る辺ない環境で成長してきました。ほんの少しの油断でも、台湾、つまり私の国はすぐに消えていくと言っても過言ではありません。そして、自分の力で頑張らなければならない現実を受け入れてから、絶対に譲れない思いが生まれました。それは自由と民主主義の台湾を守るということです。
私はSNSでもよく政治的な話をします。政治意識が高いからではなく、ただその発言をとおして台湾人や日本人に自分の周りの状況にもっと注目してもらいたいだけなのです。もちろん意見の違う人から悪質なコメントも殺到します。そして、ある人たちはこう思っている。「芸術は芸術、政治は政治」。この考えにはまったく納得出来ません。成長する国や環境によって、私たちの人格や多様な生き方は作られたのです。思うに、土地と創作はとても密なもの。だから、もしその土地が私に助けを求める時、私は黙るわけがない、ただそれだけです。

<プロフィール>
ガオ・イェン/漫画家、イラストレーター。1996年台北生まれ。台湾芸術大学視覚伝達デザイン学系卒業。2018~2019年沖縄県立芸術大学に交換留学生として短期留学。Twitter@_gao_yan
本記事は『イラストレーション』No.226の内容を本Webサイト用に調整・再録したものです。記載している内容は出版当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承下さい。
本インタビューも掲載されている『イラストレーション』No.226。2019年10月に逝去されたイラストレーター・グラフィックデザイナー和田誠さんを80ページにわたって特集しています。代表的な仕事の紹介はもちろん、親交のあった方々からの寄稿、オマージュイラストなど盛りだくさんの内容です。