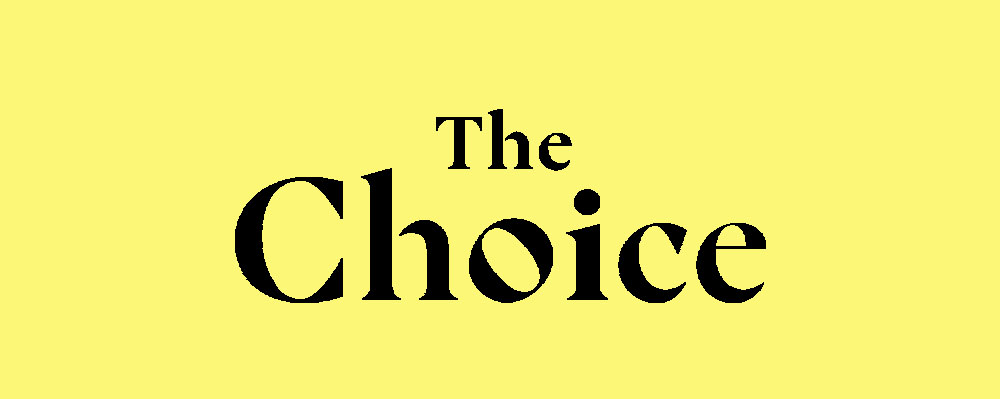『イラストレーション』No.228に掲載されたイラストレーター木内達朗さんとグラフィックデザイナー大島依提亜さんの対談を前後編でお届けします。
木内さんと大島さんが共に手がけたウディ・アレン監督作品「レイニーデイ・イン・ニューヨーク」の映画ポスターは、SNSなどで拡散され、大きな注目を集めました。今回はお2人に、その制作の貴重な舞台裏をたっぷりと語って頂きます。
協力:一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ、有限会社ロングライド
(前編はこちら)
2つのポスターにこめられた意味
大島:今回木内さんに依頼したタイミングは、ちょうどウディ・アレンの問題(*3)が持ち上がっていた時期でした。木内さんには、そのことも含めて相談しましたよね。
(*3)ウディ・アレンの問題……2018年、ウディ・アレンは養女への性的虐待問題で再告発された。訴訟には勝訴するものの、そのスキャンダルによって「レイニーデイ・イン・ニューヨーク」はアメリカ本国での公開が見送りとなった。
木内:はい。だけど僕は、その時はあまり問題を理解していなかった(笑)。
大島:そうそう。結構やばい案件だって伝えたのに、「大丈夫じゃない?」って軽い感じだった。だけど後から調べて「これはまずいかも」って思ったでしょ(笑)。
木内:うん……。まあ、今回は無罪ってことだから……。でも、もしウディ・アレンが有罪だったとしても、大島さんはこの依頼を引き受けたんですか?
大島:えーと……、僕はそうですね、受けたと思います。僕自身、ウディ・アレンの作品は大好きですが、それでも作品と彼の問題とを切り離すことは出来ないと感じています。だから、今回の依頼はかなり悩んだんですけど、自分はこれまでにウディ・アレン作品を何作も担当してきた経緯があるし、落とし前としてやろうかなと思いました。
木内:そういうところは、最近特に悩みますよね。この仕事は受けていいんだろうか? 受けるべきなんだろうか? というような。たとえば、差別を扇動するような本の依頼がきたとしたら、やっぱり大島さんは断りますよね?
大島:それは絶対やらないですね。
木内:じゃあ、そういう本を出している出版社の別の仕事はどうですか。突き詰めると結局何も出来なくなってくるなとは思いつつ、悩みます。
大島:確かに、過去のものまですべては追えないですよね。難しい問題だけど、その場合は出版社というより、編集者と編集内容で判断するんじゃないかなあ。
いまは映画1つとっても、差別的なものや多様性を無視した作品自体、もうありえない時代になっています。昔のコメディを改めて見ると、当時は普通に観ていたことでも、いまはもう笑えない場面がある。でも、そうやって文化が深度化していくのは当然だし、そのこと自体は前向きに捉えられると思うんです。レイニーデイのポスターは、まさにその部分を真面目に入れたいって思ったんですよ。

木内:それは、どういうことなんでしょうか?
大島:僕、この映画を緊急事態宣言下で観たんですね。でもその時期に観た映画は、街に人が歩いているシーンでさえSFのように感じてしまって、普通に楽しむことが出来なかったんです。だけど、レイニーデイだけは違いました。ウディ・アレン自身の問題は意識的に考えざるを得ないんだけど、閉塞感のあるいまから解放してくれるような不思議な映画に感じたんです。きっとそれは、ウディ・アレンがずっと描いてきたニューヨークの街並みが、コロナ禍に勝るくらいの強度だったからなのかなと思います。
だから今回作るポスターは、「外」と「中」の対比で、ニューヨークを象徴する背景の中に人物がポツンといる、というイメージをはっきり持っていました。そうすることで、かなり間接的・観念的にではありますが、コロナ禍という状況下での環境と人のあり方、延いては、ウディ・アレンの問題についても、このポスターにこめられたらなと思ったんです。
木内:大島さんからはイメージの共有と共に、どこを描くかの具体的なディレクションもありましたね。それで、「外」は雨の日のセントラル・パーク、「中」はメトロポリタン美術館の場面を描きました。
大島:セントラル・パークの方は、映画にはないシーンだったのに、あたかも登場していたように感じます。奇しくも、実際のシーンと想像のシーンという対比になりましたが、描き方に違いはありましたか?
木内:それは、あんまり意識しなかったかもしれません。セントラル・パークの絵は、想像とは言ってもGoogleストリートビューで実際に歩いてみて、ここだったら建物も見えて緑もあっていいかなと、考えながら場所を決めたので。
大島:その口ぶりだと、ストリートビューに現れる図像を参考にするというより、歩いて様子を見に行くという感じなんですね。
木内:美術館の方は、スチール写真を見て描いたんですが、部屋にあった像などは省略している部分があります。あと、実はこの部屋の壁にかかっているのが、僕の好きなサージェント(*4)の絵で……。全部知っている作品だったので、模写をしているようですごく楽しかったです。
(*4)ジョン・シンガー・サージェント……アメリカの画家。1856~1925年。代表作の「マダムXの肖像」はメトロポリタン美術館に所蔵されており、木内さんによって、今回のポスターの絵にもさりげなく描かれている。

大島:全部知っているのはすごいですね。模写とはいっても、かなり簡略化が必要ですよね。デジタルの場合って、描こうと思えば際限なく描けちゃうと思いますが、その塩梅はどうしてるの?
木内:難しいですね。あんまり描きすぎても主役の2人が目立たなくなってしまうので、僕はなるべく拡大せず、細かくなりすぎないようにサムネイルくらい大きさで描いています。主人公のディテールだけ、最後に拡大して描きこむ感じですね。
大島:細かく描いちゃうと、絵として成立しないということなんでしょうか。
木内:そう思いますけど、人によっては満遍なく同じ力で描く人もいますよ。意図してやっているのであれば、それはそれでいいんじゃないかなと思います。
大島:完成した絵を見た時に、引きで人物がポツンといる感じが、2人の距離感や関係性を際立たせるようで、すごくいいなと思いました。木内さんが海外でしている仕事を見ていると、日本でしている装丁装画の仕事とは、ガラッとイメージが違う印象があって。だから、日本発のカッコいいポスターを、木内さんの絵でやりたいとずっと思っていたので、今回それを実現出来たのがめちゃくちゃうれしかったです。
木内さんのYouTubeには、ポスター制作の過程を記録した動画がアップされている。
映画ポスターだから出来るチャレンジ
大島:そういえば、この前木内さんが「うまく描けた」と言っていた作品があったと思うんですが、木内さんの言う“うまく描けた”って、一体どういうことなんですか?
木内:「少年と犬」(B)の挿絵のことですね。これは、車のヘッドライトが動物に当たった時の光を、自分が頭に思い描いたとおりに描けたんじゃないかなと。

大島:それって、作家にしか分からない感覚かもしれない……(笑)。この絵はモノクロだけど、カラーとモノクロとで大変さややりがいに違いはありますか。
木内:僕の場合は、絵の中での配色や、そのハーモニーを表現するのに一番気を使うんです。だから、モノクロだと色の調和について全然考えなくていいので楽ですね。逆に言うと、色が気に入っていればどんな絵でもよく思えてしまいます。
大島:楽っていう感覚なんだ。これってグレースケールで描くんですよね? ということは、階調の差だけで描き分けている。
木内:はい。でもカラーの場合と違って、モノクロだと真っ黒と真っ白が使えるので。
大島:え、ということは、木内さんってカラーの時は完全なブラックを使わないんですか?
木内:仕事の絵ではあまり使わないですね。自然の中の “黒”は、実際にはそれほど黒じゃない色ですし。それに、モノクロの“真っ黒”と同じ明度をカラーで表現しようとすると、必然的に完全なブラックを使うことになりますが、カラーの絵にはすごく暗い部分でも色を使いたいのです。ただし、グラフィック的にデザインとして引き締めるために、真っ黒を使うことはあります。
大島:ハイライトに紙地の白を使わないのは理解出来るんですけど、黒も使わないというのは意外。犬の脚は真っ白を使っているけど、ここはどうして?
木内:文芸誌って再現性がそれほどよくない紙なので、なるべくコントラストを強めに出したいなと思って。もし一般誌に載るんだとしたら、ちょっと浮いちゃうような気がします。実際そんなに白くはならないはずだし。

大島:なるほど。色の方向性をゼロベースで決めないとならない場合には、ここだけが際立っちゃうのか。面白いなあ。
木内:僕からも大島さんに質問があって。大島さんって、これまでにコンペの審査をたくさんされてるじゃないですか。コンペで選ばれる絵ってユニークで芸術性のありそうな作品が多いと思うんですが、実際の仕事ではどういう絵があがってくるのか想像しにくい部分もあるのかな、という印象があります。
大島:なるほど。それこそさっきの、ファインアート的なのか、イラストレーションなのか、っていうことですよね。
木内:はい。まさにそうで、僕が青山塾で教えていると、コンペでは入選しなくても仕事にはなりそうかなと思う絵もあるんです。そのあたり、大島さんにはどう見えているんだろうと。
大島:確かに商業ベースになる絵でも、現状のきっかけとしてコンペがある以上はスタート地点に立てない絵とも言えるわけで、かなりジレンマがありますね。僕自身、コンペに関しては仕事として活躍出来る方を選ぼうという観点は持っています。でも最終的に、 “声が小さいけどいい絵”に惹かれがちなんですよね。ただ、そういった作品の場合、かなりシチュエーションが合致する仕事じゃないとお願い出来なかったりするので、結果的にあまりご一緒する機会がないのが現状かなあ。
木内:なるほど。意外とチャンスがないですか。ちょっと気になっているのは、特に広告ですが、誰も使っていないユニークでインパクトのある新人を見付けたもの勝ちで、1度使ったらまた次の人を探すということの連続、一方でベテランの人はあまり使わない。みたいな傾向があるような気がして……。
大島:確かに、ちょっと残酷な形になってしまっている部分はあるのかもしれません。実際、僕も装丁に関しては比較的新しい人に頼む場合があります。どうしてかと言うと、自分自身が装丁家ではないという意識があって、どうしても、違う切り口で見せたいという気持ちが働いてしまうんですよね。
ただ、映画についてはまったく逆。確実にクオリティの高いものを作りたいので、キャリアのある方にお願いすることがほとんどです。確かに、 “見たことのない作風”という新しさもあるとは思うんですが、僕はキャリアのある人に新しいチャレンジをしてもらって、イラストレーションとデザインが合致した時にこそ、より創造的で新しいものが出来るって信じています。
木内:僕も、イラストレーションなんて全部デザイナー次第だって思っているところがあるんです。自分だけじゃいつもと同じ絵しか描けないし、デザイナーのディレクションがあるからこそ、いい絵が描けるんじゃないかなと思います。
大島:今回木内さんと一緒にやらせてもらった映画のポスタービジュアルって、装丁装画とは違う、描き手の新しい側面を示唆出来ることもいい点だなと感じています。さっきも言ったんですが、僕は、日本にいる素晴らしい描き手のことをもっと世界に知らしめたいんですよね。だから、これからも映画ポスターという形で、その役割を果たしていけたらなと思います。
<プロフィール>
きうちたつろう/イラストレーター。1966年東京生まれ。国際基督教大学教養学部生物科卒業後、渡米。Art Center College of Design卒業。ニューヨーク・タイムズをはじめとして雑誌、書籍、広告などの仕事を多数手がける。
おおしまいであ/グラフィックデザイナー、アートディレクター。東京造形大学デザイン学科卒業。映画のグラフィックを中心に、展覧会や書籍のデザインを手がける。最近の仕事に「万引き家族」や「ミッドサマー」「デッド・ドント・ダイ」映画宣伝物など。
本記事は『イラストレーション』No.228の内容を本Webサイト用に調整・再録したものです。記載している内容は出版当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承下さい。

今回対談も掲載されている『イラストレーション』No.228では、画家のnakabanさん、絵本作家・イラストレーターの植田真さんを大きく特集。それぞれの多岐にわたる活動に加え、2人が共に手がけた絵本や展示についてもご紹介します。

『木内達朗作品集 TATSURO KIUCHI』は多岐にわたる仕事の原画やオリジナル作品から木内さん自身が厳選。シニカル&ナンセンスなユーモアが伝わるマンガや、ブログに掲載したエッセイも収録されています。